どうも。ぞうさんです。
毎日の食事、おいしく食べていますか?
もうすぐ梅雨の時期がやってきますね。そこで注意していただきたいのが【食中毒】です。
なにせ私も食中毒を発症し、数日間格闘した経験があります。
実は梅雨の時期が最も発生率が高くなる時期なのです。
ということで、今回はその原因と、予防方法をご紹介します。
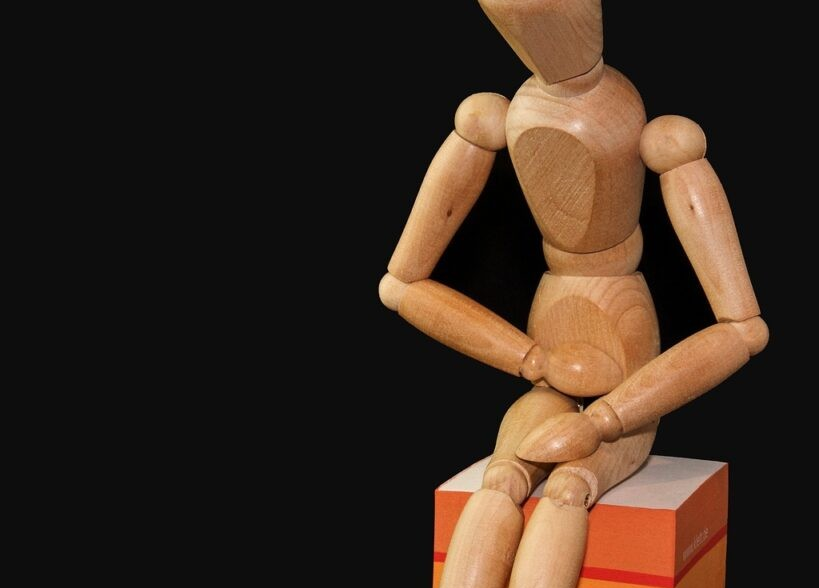
目次
●まとめ

食中毒にならないための予防具体策
細菌を【つけない】【増やさない】【やっつける】
上記の3原則を踏まえた具体的予防策が厚労省に掲載されているので、添付します。
厚労省の資料を見る中で、私は特に今まで気にしていなかったのは、魚や肉の汁についてです。
普段冷凍することが多く、解凍した際に冷蔵庫内で肉からの汁がラップからあふれてしまっていることがありましたが、特段気にせず普通に拭いていました。
しかし、これも食中毒の原因となりうるので、今後は注意しなくてはと思いました。

食中毒の発生率が高くなるのは湿度の高い【梅雨の時期】
まずそもそも食中毒とは、飲食物内に含まれる有害物質を摂取することにより発症する症状を言います。
代表的な有害物質は、黄色ブドウ球菌・O-157・サルモネラ菌・カンピロバクター
などが有名でしょうか。
その原因は、細菌の増殖のしやすい環境が【栄養素】【温度】そして【湿度】に影響するからです。
つまり、湿度の高くなる梅雨の時期が細菌が最も増殖しやすいため、発症率が高くなるということです。
食中毒を発症しない・させないための対策として、【食中毒予防の3原則】というものがあります。
それは…
まとめ
実際に食中毒を経験して、もうあのような目にあいたくないと思っていましたが、注意しなければならないのに注意していない点が今回調べてみてわかりました。
症状が軽ければ腹痛や嘔吐で済むそうですが、場合によっては命に係わることもあるそうです。
食事は人間が生きる上では必ず行う行為です。
皆さんも家族を守るため、そしてなにより自分自身を守るために、衛生管理をしっかりと心がけ、毎日の食事を楽しみましょう。




コメント